説明責任を知らなかっただろ?
「私が同志社大学大学院商学研究科修士課程で大学教員になるために監査論の研究を開始して以来一貫して研究スタンスのコアにあった『アカウンタビリティ=説明責任』という言葉」と偉そうに書いたが、正直言うと、私が商学部助手として研究者生活をスタートさせた1973年当時、「アカウンタビリティ」は「説明責任」とは訳されていなかった。「会計責任」と訳された会計学領域の専門用語だった(と、私をはじめ多くの会計学徒は思っていたはず)。
「アカウンタビリティ」が「会計責任」という訳だけでないことに気づいたのは、2度目の留学でイギリスのレディング大学マンスフィールド学寮に住むようになってしばらくしてからのことだった。イギリスのTVを見ているとサッチャー首相をはじめとするイギリスの政治家たちはみんな実によく喋るのだ。マスコミのインタビューに対しても、日本の政治家のように木で鼻をくくるような素気ない、わざとポイントをずらした答弁ではなく、実に丁寧に説明する。私は不思議で仕方がなかった。
このことがいつも気にかかっていたので、ある日、寮の事務長のヴァルに「イギリスの政治家はどうしてこんなに詳しく説明するのか?」と尋ねた。すると彼女は、不思議そうな顔をしながら、「そりゃ、政治家にはアカウンタビリティがあるからだ。十分な説明をしない政治家には次の選挙で投票しない」と当然のように言い放った。
彼女の説明を聞いて、私の脳裏には、「どうしてヴァルは『会計責任』という会計の専門用語を知っていて、政治問題にこの言葉を使ったのだろう」という素朴な疑問が浮かんだのだった。(今となっては、私の無知を恥じるしかない。)
翌日から大学の図書館で「accountability」について調べたところ、驚くべきことがわかった。「accountability」は「会計責任」と訳されるだけではなかった。会計学の専門用語ではなかったのだ。教育学の分野では「教育責任」と訳され、財政学の分野では「財政責任」と訳されていた。いずれも、それぞれの分野で「説明する責任」を意味していた。
実は、1977年から担当し始めた監査論の講義を、私は次のような説明で始めていた。「英語では、会計学はaccounting、会計士はaccountant、と言います。語源は、accountという動詞で、通常forという前置詞がくっつく『説明する』という意味です。企業が財務諸表を用いて利害関係者に財務状況を『説明する』のが会計というわけです。」まさに前段部分が正解だったのだが、後段部分に囚われ過ぎていた。
イギリスを留学先に選んだのは「大正解」だった。

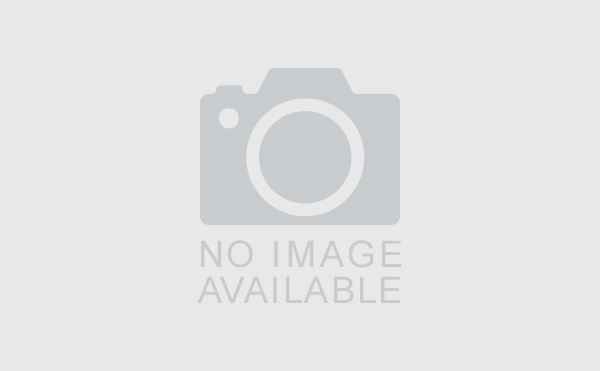
自民党に今のような回答の仕方、よく言われる”ごはん論法”を教えたのは一体誰なのか?
いつも気になる。 自民党お抱えの弁護士事務所なんだろうか?
たしか、上西充子教授から一番最初に”ごはん論法”と非難されたのは、 加藤が厚生労働大臣の時だと記憶しているが・・・
それ以来、安部以下すべての閣僚がごはん論法、論点ずらし論法を駆使している。
ある意味、 会見でのマスコミの突っ込みが全くなくそれらの傾向を助長している。
マスコミの劣化が悲しい!!
イギリスのインタビュアーの突っ込みは強烈ですね。答える方もごまかしがきかない。カッカせずに答えるのは難しそうですが、幼少期からの訓練でしょうか。日本でやったら、まともに答えられる政治家はいるのでしょうか。聞く方も答える方も訓練しないと、うやむやに終わらせる文化は変えられないのでは。
先生とお会いしたら絶対聞きたいと思っていた制度があります。Intergeneration-equityという英語で世代間の公平と訳されますが、果たしてこの制度はどういうものなのでしょうか。
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/intergenerational-equity
Intergenerational equity in economic, psychological, and sociological contexts, is the idea of fairness or justice between generations. The concept can be applied to fairness in dynamics between children, youth, adults, and seniors. It can also be applied to fairness between generations currently living and future generations.
いろんなことでこの制度は使われているようです。日本ではこのような取り組みがありますか?